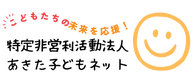学習支援の目的
子どもたちは、家庭や学校の枠を超えた多様な環境の中で成長していきます。生きる力を育むには、学力だけでは不十分であり、コミュニケーション能力や問題解決能力といった非認知能力が重要です。非認知能力は、学校で習うことを理解するための土台でもあります。
学校での学習時間(年間約1200時間)よりも長い放課後の時間(年間約1600時間)は、学校の宿題をする時間のみならず、非認知能力を育む大切な時間と言えるでしょう。子どもたちが学校の先生や家族以外の人と関わったり、「できた」「分かった」という成功体験を積み重ねたりすることは、自己肯定感やソーシャルスキルトレーニングにつながります。
すべての子どもの成長を見守る中で、相対的貧困家庭の子どもや、障害のある子ども、定型発達や愛着形成を獲得できない子ども、他にも様々な事情で学習の機会や人との関わりが限られがちになる子どもがいます。そのため、学校で習う内容が理解できないなど、陰性症状として不登校になることもあります。
一般的な学習塾も、子どもが学力を伸ばし、将来の進路を切り開く学びの場です。しかし、経済的な理由や、障害を持つために、一般の学習塾に通いたくても通えない子どもが存在する現実があります。生まれた環境によって学びの機会が左右されることは、子ども自身の可能性を狭めるだけでなく、貧困の連鎖を生み、社会全体の格差を固定化させる要因にもなります。学習の機会の損失に何かしらの対策を行わないと、将来的に就労できずに社会的孤立を招くことから、日本全体の生産性の低下や経済損失が懸念され、相対的貧困状態にない人たちにとっても関わりのあることと考えられます。
このような課題に対して、学校外の地域資源として、学習の場(あるいは居場所)が数多く存在することが大切だと考えます。数が多いほど、子ども一人ひとりに合った居場所を見つけられる可能性が高まるからです。
私たちの設けている学習スペースは、学校の休日や長期休みの際に、学校での学習を定着させるためのサポートを行っています。同時に、子どもが行きたい場所、自由に過ごす場所でありたいと考えています。子どもの気持ちを大切に、安心して学べる場づくりを行うとともに、非認知能力を鍛える遊びや活動体験も取り入れた、地域資源の一つとしての学習支援を行います。
学習支援は、未来の社会への投資とも言われますが、それだけでなく、いま生きている子どもたちを見守ること、保護者に「子どもの成長を見守る存在」として安心感を持ってもらえることを目指し活動に取り組みます。